筆者の自作小説です。カクヨムの方にも投稿しています。
長いため分割して投稿します。
本文は以下から。
『夕日に揺らめく』
――1日目。
「私はカゲロウ。人間になったカゲロウだよ」
柔らかに語られたのは、到底信じられないファンタジーだった。
紅くなった空を背景にして、彼女の輪郭はほとんど消えかけていた。それは、思わず手を伸ばしてしまいそうなほど、儚かった。
春の陽気が微かに残り、新生活にも慣れてくるこの五月。新鮮だった空気も落ち着いてくる中、いまいちモチベーションが上がらないことで悩んでいる人も多いことだろう。
俺もその一人だ。今年に受験を控える身だが、どうしてか勉強に向かうことができない。これでも新年度が始まる前後の頃は、気が立っていたのか毎日七時間は勉強しようと息巻いていたし、実際にそれに近い量をこなしていた。
しかし、些細なきっかけで集中の糸が切れてから、それまでの勢いはどこへやら、まるっきり勉強をしなくなってしまった。
やる気の問題だと言われるのは当然だけど、そういうことを言う人は大体、こちらの精神状態を知らない。
やる気はある。だから今まで六、七時間の勉強を続けてこられた。
でも今は、身体が言うことを聞かない。勉強しなければという意思に反して、身体は机から遠ざかる。勉強も他のことも何もやらず、無益に一日を消化してしまう日もあった。
翌日に後悔をするも、虚しくなるだけ。その虚しさを埋めようと焦るのだが、やはり身体は動かない。自分で自分を責め、結局一日を無駄にしてしまう。
この負の連鎖が、不安を煽る。波のように寄せては引いて、俺のメンタルをじわじわと削っていく。
そんなわけで、俺のゴールデンウィークは最悪だった。約一週間の休みを、俺は何の役にも立てることが出来なかった。受験生としてあるまじき行為だ。許されない。
後悔しても取り戻すことが出来ないのは分かっているのに、どうしても思考はネガティブな方へと引っ張られる。
最終日にはとうとう、学校に行きたくないとまで思うようになってしまっていた。
しかし同じ日に俺は、とある出会いをした。それはちょっとした外出から帰ってきたときのことだ。夕方だった。
不思議な女の子が俺の部屋にいた。
全身は泥にまみれ、髪は針金のように硬い。おまけに、鼻が詰まりそうな異臭を部屋中に漂わせていた。
そして、彼女は言った。
耳を疑った。何かのイタズラかと思った。それとも、五月病で俺がおかしくなっただけかとも思った。
何度も何度も問いただした。名前は何か。どこに住んでいるのか。それでも、女の子は自分を蜻蛉だと言って止まなかった。
俺だけではどうしようもなかった。だから母さんにもこのことを知らせた。母さんもこの女の子の来訪には目を丸くしていた。
その日の夜にじっくりと話し合った。察しのいい母さんでも、このことを信じるには時間がかかった。無理もない。
日付が変わる程の話し合いの結果、ひとまず女の子が人間になった蜻蛉であることを認めた。家が無いと言うこの女の子は、母さんが面倒を見るということで俺の家にかくまうことになった。
それが、俺とカゲロウとの一週間の始まりだった。
――2日目。
ペンを弄び、参考書も上の空で、俺は昨日のことを思い返していた。
カゲロウとの出会い。虫が人間になったという衝撃の告白。時間はかかったもののカゲロウを受け入れた母さん。
そして、残された時間のこと。
「ねえ、何やってるの?」
「ん? ああ、勉強だよ」
机に広げた新品同然の参考書や二、三ページしか書いてないノートをカゲロウが興味津々に見ている。身体を寄せていて、顔なんかほとんどくっつくほど近い。昨日の強烈な匂いがまだ鼻腔に残っていて、俺は思わず身を引いた。
「ちょっと、なんで避けるの?」
「あ、ごめん」
実は避けたのは別の理由だったりする。
昨日、母さんが風呂で念入りに洗ってくれたおかげで、今のカゲロウはすっかり綺麗になっている。肩にかかる程度の髪は、羽毛のように軽い。服も綺麗なものを着ている。良い匂いだってする。
清潔かどうかについては全く問題ない。喜ばしいことだ。
しかし問題なのは、カゲロウが思った以上に美少女であることだ。
別に恋愛の対象になるとかそういうものではない。でも考えてみてくれ。顔の整った少女がくっつくほど近づいてきたら、誰が高鳴る鼓動を抑えることができるんだ。
「ふーん、なんか難しそうだね」
全然難しく思ってなさそうだな。
「そりゃあ、まあ。難しいよ」
「なんでこんなことしなきゃならないの?」
「それは……」
流石はカゲロウ。思いもよらない質問をポンとしてくる。しかもその質問ってのがまた、俺が現在進行形で悩んでいることなんだよな。
もちろん、答えることはできない。どうして勉強をするのか。そんなこと、分かっていればこんなに苦労していない。むしろ俺からカゲロウに聞きたいくらいだ。猫の手も借りたいというか、蜻蛉の知恵も借りたいってところだな。
俺は受験生だ。受験生は、勉強をしなければならない。俺はその文句に半分洗脳されているようなものだった。
俺、受験生。勉強、やる。
なぜ勉強するのか、そんなのは知らない。黙ってペンを動かしていればいい。
そんな調子で勉強をしていたものだから、ふと雑念が入ったとき、俺の手は止まった。
『俺がこの先、できることは何だ?』
果てしない受験勉強の、その先にあるもの。もちろん大学なんだけど、そうじゃない。大学よりも、もっと先の話。俺が行き着くところは、何だ? 俺は何になって、何をして、そして何を残して死んでいくんだ?
考えた。考えて、考えて、何も分からなかった。いや、言い直そう。何も無かった。
俺がこの先するであろうことはみんな、他の人でもできる。
俺には尖った才能がない。他の人よりも努力することもない。特に秀でた能力もなく、その他大勢に埋もれている。つまり俺は人並み、凡人だ。
社会に出て、何らかの組織に入って、歯車の一つとして生きる。その歯車は、取り替えが出来る。だから、その歯車にこだわる必要はない。その歯車が出来る仕事は、他の歯車がやっても同じこと。
俺がいなくても社会は回る。じゃあ、そこに無理をしてまで入っていく理由は何だ?
唯一無二になる。社会で、俺にしか出来ないことをする。そして、俺にしか残せないものを残す。
だってそうじゃなければ、俺が生きている意味がないじゃないか。
それ故に、俺は自分の能力に絶望している。自分の能力では、人並みのことしかできない。
だめだ、またそうやってネガティブな方へと考えてしまう。だから。だから全く勉強が進まない。
「どうしたの? すごく怖い顔だよ?」
思考が深いところまで入ってしまっていたようだ。カゲロウが心配そうに俺の顔を覗いていた。
「いや、何でもない」
「そうなの? 私には、嫌なことがあるみたいに見えるよ?」
「…………」
否定はできない。
「あ。もしかして、これやりたくないの?」
カゲロウは自信たっぷりに机を指した。やりたくないって、また随分とざっくりとした言い方だ。
「間違ってはいない」
「なにそのハッキリしない答え」
「やりたくないけれど、やらなきゃいけないんだよ」
「どうして?」
「またそれか。さっきも聞いてきたじゃないか」
「だってさっきは答えてくれなかったじゃん」
「…………」
「また答えてくれない!」
プンスカ、という擬音がしそうなくらい、カゲロウは顔を真っ赤にする。感情の変化が分かりやすい。まるで子供だ。ここで拗らすと手のかかることになりそうだ。
「分かった分かった。じゃあ話すよ」
カゲロウは素直に頷いて、聞き耳を立てた。
「あのな、虫にはよく分からないと思うけれど、俺は凡人なんだよ。俺が出来ることは他の人も出来る。だから、俺がする必要はない。そう思うと、どうしても勉強のやる気が出なくてね」
何かに気づいたように、カゲロウが息を吸い込んだ。
「ん、どうかした?」
「私と一緒だ」
「え?」
「それ、私もそう」
「ちょっと待って、言ってることが全然分からない」
分かってもらえなくて不満なのか、カゲロウは口を尖らせた。
「だから、私も同じなんだよ」
虫だからなのかそれとも人間として単に能力が足りないのか、カゲロウは上手く自分の気持ちを言葉に出来ないのだろう。同じことしか言ってない。
「つまり、カゲロウも虫の中では凡人、いや、凡虫? まあどっちでもいいけど、凡人だから、何かやる気が出ないってこと?」
言いたいことをフォローしてやると、カゲロウは何度も頷いた。
「そういうことそういうこと。だから私は――」
『二人ともー。ご飯できたよー!』
カゲロウが何か言いかけたところで、母さんの声が遮った。幼ささえ感じる母さんの高い声は下の階からでも良く聞こえる。
「あ、はーい!」
カゲロウはそれまでの会話をそっちのけで、一階へ降りていってしまった。
「え、終わり?」
カゲロウが開け放ったドアに向けてツッコミを入れる。あまりにもあっさり話が終わってしまい、少々困惑。
仕方無く、参考書を閉じて席を立った。
外はいつの間にか暗くなっていた。
昨日のことはまだ鮮明に覚えている。夕日もほぼ落ちかけ、昼と夜の境が曖昧になっていたあのとき、この部屋でカゲロウと出会った。
『どうしたのー? 早く早くー!』
下からカゲロウの急かす声がした。
「あ、すまねえ。今行くよ」
部屋を出る前に立ち止まって、振り返る。
勉強机に、黒く影がかかっている。照明を落としたからなのか、それとも別の理由があるのか。
「……本当は、自分が一番分かってるくせに」
今日も、勉強は全く進まなかった。
カゲロウのおかげで食卓はいつもより三割増しで賑やかだったけれど、喉を通るご飯はいつものように、味気ないものだった。
次回のお話(2/5)はこちらから。

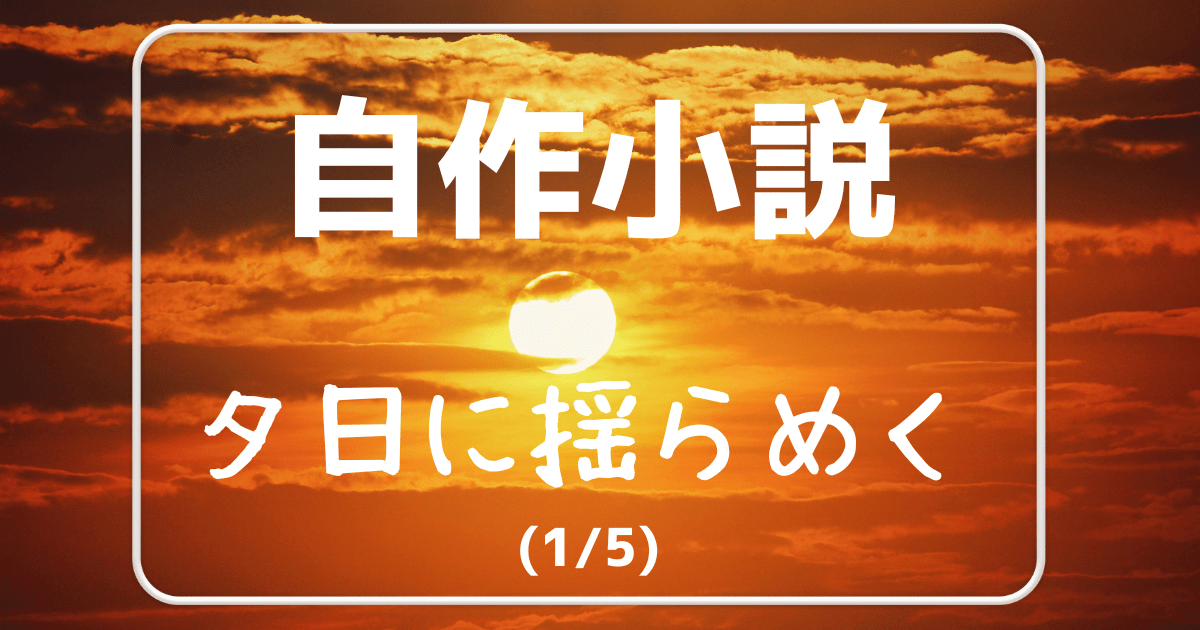







コメント