前回はこちら。
今回で完結です。
最後までお楽しみください。
毎日のように曇りか雨の日が続いている。この日はその中でもとびきり寒かった。芯から凍えそうな上に、雨も冷たい。
そんな日なのに、大学で見かける連中の表情はどこか明るかった。そういえば、もうすぐクリスマスだっけか。
寒さから逃げるように研究室に入ると、蓮花の姿があった。
「あっ」
という声が重なる。
「ど」
上ずった声で蓮花が言った。
「どうしたの? 元気なさそうだよ?」
笑顔もぎこちない。努めて平然としているのが丸わかりだった。そんな健気なところを見せられたら、言いたいことも言えなくなる。
「いや、少し考えごと」
「どんな?」
「それは、ちょっと言えない」
「何で? 教えてよー」
見ていられなくて、僕は目を逸らした。
もう切り出していいだろうか。蓮花のことを考えて、今日はやめた方がいいだろうか。
いや、それだといつまでも何も変わらない。真田さんにそう言われたじゃないか。
「あのさ」
「ん?」
「この前のことなんだけど」
瞬く間に蓮花の目がにじんだ。
「あれはさ、やっぱり――」
「あーあー。もう大丈夫聞きたくないから」
蓮花は耳を塞いだ。涙をこぼさないように目もギュッと瞑っている。
「蓮花。頼むから聞いてくれ」
声をかけても、彼女は頭を振り回して聞こえないふりをしている。これでは話にならない。
「蓮花!」
声を張り上げると、蓮花は怯えた子犬のようにこっちを見た。こらえきれなかった雫が一筋、頬をつたった。
やっちまった。取り返しがつかなくなってももう遅い。こんなせっかちなのは、きっと夏実のせいだ。
「あの夜のことは、もういいから。蓮花は悪くない」
蓮花は口を開いたけど、言葉が出てこない。
「あのとき、素直にダメって言わなかった僕が悪い。蓮花に変な期待させてしまった。傷つけたくないと思ってたけど、そのせいで余計に辛い思いをさせてしまった。ほんとにごめん」
僕はまくしたてる。一度でも止まったら、もう何も言えないだろう。
「僕には好きな人がいるんだ。いつも真っ先にその人のことを考えてしまうくらいに。だから……」
けど僕は言葉に詰まった。擦り切れた雑巾みたいに、蓮花はぼろぼろと泣いていた。
今すぐにでもこの場から逃げ出したかった。自分のせいで目の前の女の子が泣いている現実を直視したくなかった。
でもそれではダメだ。自分がどうしたいのか、はっきりさせなければ、また同じことを繰り返す。心を鬼にするんだ。
「だから、蓮花とはつき合えない。ごめん。ほんとに、ごめん」
心の中では、その何十倍も謝った。
「でも、蓮花のことが嫌いなわけじゃない。また今度、飲みに行こうよ」
蓮花は何度も鼻をすすり、声を漏らすまいと唇を噛んでいた。手のひらで何度も頬を拭い、それでも時々こらえきれずに低い声が出た。
僕はいてもたってもいられず、蓮花に近づいた。でも、彼女はそれを手で制した。
やがて落ち着いてくると、涙の混じった声で蓮花は言った。
「もっと早く言ってほしかった」
「…………」
僕は何も言い訳をしなかった。
袖で目元を拭いて、蓮花は笑った。
「でもありがと」
その笑顔は、眩しいくらいに輝いて見えた。
でも、これ以上はもう限界だった。
「ごめん、ちょっと、トイレ」
蓮花はうつむいたまま研究室を飛び出していった。
「……ごめん」
取り残された僕は、もう一度だけ、謝った。それから、安心感と罪悪感が同時に襲ってきた。こんなこと、二度と味わうことはないだろう。もちろんそれを心から望む。
でも、これで終わりじゃない。本番はこれからだった。
建物を出ると、僕は夏実に電話をかけた。メッセージでなく、声で伝えた方がいいと思った。
長いコールの果てに、彼女が出てきた。感情のない声だった。
『……もしもし』
「もしもし間庭だけど。今、時間ある?」
『……あるけど』
電話越しなのに、彼女の声が聞こえる度に心臓が跳ねあがる。今からこんな状態で、実際に対面したら僕は死ぬんじゃないか。
「話したいことがあるんだ。ああ、電話でじゃなくて、もっと大事なこと。だから、さ、今夜、どこかで会えるかな」
沈黙は長かった。二度、電話が切れていないか確認した。
「イヤだったらいいよ。でも、このままでいるのはお互いによくないと思うんだ。だから」
もう一度、念を押すように電話口に語りかける。でも、夏実の返事はない。
外は雨が降っているのに、気味が悪いくらいに静かだった。外を歩く人影もない。何だか、自分だけが違う世界に取り残されているようだった。夏実の声だけが、元の世界とつながる最後の希望のように思えた。早く、返事をしてくれ。
やがて、夏実はやけに事務的に返事をした。
『サー棟の駐車場。夜十時』
「頼む」
約束をすると、向こうから電話が切れた。でも、それだけで十分だった。
一時間も前から僕はサー棟にいた。傘をさして夏実が来るのを今か今かと待っている。僕の他にも誰か残っているようで、いくつか明かりの点いた部屋があった。
雨はいつの間にか雪に変わっていた。今季になって初めてだ。ほんの小さい白い塊が音もなく真っすぐと落ちて、アスファルトに染み込んでいく。
寒さに耐えかねて、僕は車に乗り込んだ。エンジンをかけて、エアコンを入れる。オーディオから『テイク・オン・ミー』が流れ出した。夏実の趣味だ。
アップテンポなシンセサイザーを聞き流しながら、僕はシートに深く身を預けた。
夏実が来たら、何て言おうか。今までの不甲斐ないことを謝って、それから自分の思いを打ち明けようか。いや、そんな回りくどいこと、夏実は好まない。なら、ズバッと素直に告白してしまおうか。でもそれだけだと何も伝わらない気もする。
思い返せば、僕は夏実に振りまわされっぱなしだった。彼女の言うことに頷いているだけで、自分から何かをしたことがない。
彼女を支えてやれる人が必要だ、と真田さんは言った。真田さんは何でも知ってるし、何でもしてくれる。そんな真田さんでさえ彼女を変えることができない。
結局、夏実を支えられるのは車だけなのだろうか。そう思うと、途端に自信がなくなってきた。
車。
夏実が車に求めているのは、絶対に裏切らないことだ。
「……そうか」
ひらめいたかもしれない。
支えるというのは、何もこちらから働きかけるだけじゃない。全力で向かってきた相手を受け止めてやるのだって、同じことなんじゃないか。ステアリングを握れば手足のように応えてくれる車のように、彼女を受け止められれば。
いや。
頭を振った。そうじゃない。それでは、今までと同じだ。
僕がしてやらなければならないのは、夏実が本当に求めているものだ。それは、ただ受け身でいることじゃない。
だったら、何だ。彼女が欲しいものって。
駐車場のアスファルトが、うっすらと白い膜を張っていた。落ちてくる白い塊が、先ほどよりも大きくなっている。みるみるうちに、僕の車を厚く覆っていく。
ふと、リックアストリーの曲が耳にとまった。これも何度も聞かされて耳で覚えてしまった。なんとなくサビを口ずさんでみた。
絶対あきらめない。絶対見捨てたりしない。泣かしたりしないし、傷つけたりもしない。
時代は古いけど、いつだって好きな人にはそうあるべきだ。でも――
逆に、夏実を攻撃してみたら、どうだろう。
「まさか」
すぐに否定した。そんな自殺行為ができるかってんだ。
考えても、何も出てこなかった。ずいぶん時間が経ったような気がして、僕は腕時計を見た。すでに十時を過ぎてから、三十分が過ぎようとしていた。スマホも確認したけど、間違っていない。
夏実にしては遅い。あるいは、来る気がないのか。
僕は後者でないことを願った。会おうと言ったのは僕だけど、時間と場所を指定したのは夏実だ。彼女は約束を破ったことはない。時間に遅れたことだってない。
まだ待とう。僕は夏実を信じて待った。
しかし、十一時を過ぎても、一向に来る気配がない。やがてサー棟の部屋の電気が全て消え、周りに停まっていた車もいなくなってしまった。僕だけが、白い闇に取り残された。じわりと、胸に苦い味が広がっていく。
真田さんの言葉が思い返される。いつでも大丈夫。そう油断していると、二度と手に入らなくなる。
嫌われたのだろうか。
もう手遅れなのだろうか。
認めたくないけど、この場に夏実がいないのが現実だった。
ギアを一速に入れて、また戻す。
諦めて走り出したい気持ちが顔を出しては引っ込む。なかったことにして、どこまでも遠くに逃げられたら、それが一番楽だ。
何度も思いとどまって、とうとうエンジンを切ったとき、電話が鳴った。夏実からだった。
食いつくように電話に出た。
「今どこ!?」
『病院』
「は……?」
目の前が真っ暗になった。
電話の向こうで、荒い息づかいが聞こえる。何が、何があったんだ。まさか、また、空を見上げて……
『迎えに来て』
「なんで……なんでだよっ!」
わけもわからず、僕は声を荒げていた。
『いいから』
夏実の声は生気が抜けたようだった。一刻の猶予もなさそうだ。
「わかった、すぐ行くから! どこ行けばいい!」
『大学病院』
再びエンジンに火をつけ、矢のように走った。
病院は嘘みたいに静まりかえっていた。外来用の駐車場に車を斜めに停め、入り口へ走る。
ロータリーのバス停のベンチに、夏実はいた。頭に包帯を巻いている。極寒の中、両手を膝についてうなだれていた。その姿はあまりにも弱く、小さかった。
そばに寄ると、夏実は顔を上げた。こっちを見ているようで、目の焦点が合っていない。十秒くらい見つめ合った後、僕だとわかるとばつが悪そうに顔を背けた。
「何してんだよ」
抑えようとしたのに、強い口調になってしまった。
「事故った」
夏実は目を合わせない。
「なんで」
「ボーっとしちゃって、それで木にぶつかって」
目の前の女の子は本当に夏実かと疑いそうになった。
でも、彼女は夏実だった。見間違いようがない。癖のある長い髪に、形のいい顔の輪郭、大きくて鋭い瞳、小ぶりな口もと。美人なくせにとんでもなくおしゃべりで、せっかちでこだわりが強くて、めちゃくちゃ強気。
こんなぼろぼろになった姿を見て、僕は胸が張り裂けそうだった。こんな彼女を見たくなかった。
「怪我はひどいの?」
「大したことない。でも吐き気がする」
弱々しく語る彼女の口から、白い吐息がもれる。僕は上着を彼女にかけて、それから隣に座った。
「寄りかかっていいから」
夏実は素直に従ってくれた。肩が触れ合って、体が震えているのが直に伝わってきた。僕は彼女の肩に手を回した。華奢な体が腕の中にすっぽりと収まった。
「頭は平気なの」
「うん。ちょっと切っただけ」
「本当に、ただの事故なの? ビーエムは?」
聞きたいことが多すぎて、整理できないまま口に出してしまう。
夏実は自分のペースで言った。
「ビーエムはまだ修理中。それで今までずっと代車だったの。でも軽だからあまり乗りたくなくて」
彼女が異常なほど軽自動車を嫌っているのは知っていた。だからといって、事故を起こすほどの運転をするなんて考えられなかった。
「間に合わなそうだから急がなきゃって、スピードを出しすぎたみたい。たぶん、いつもの車なら大丈夫だったけど、制御できなくなって」
夏実はひと呼吸置いてから、いや、と付け加えた。
「車のせいにしちゃダメだよね。いつもと違うってわかってるんだから、もっとゆっくり走るべきだった。パトレイバーのおやっさんも言ってたでしょ、人間が間違わなければ機械は悪さしない、って。ほんと、その通りだったよ」
段々と、夏実の口が回るようになってきた。でもそれは、自分を慰めているようにも見えた。
いや、実際そうなのだろう。運転には絶対の自信を持っていただけに、きっとプライドは粉々だ。おまけに乗っていたのは自分がこき下ろした軽自動車だ。
かけてやれる言葉がなくて、僕は黙って彼女に身を寄せていた。あれだけ考えていたのに、いざとなると何も出てこない。
「あーあ、これで保険の等級が下がっちゃうな。ほんとにバカなことした」
何気ない夏実のぼやきだったけど、それを聞いたとき、僕の脳裏に光が奔った。
これだ。
「……お前は救いようのないバカだよ」
「え?」
「バカな運転するからこんなバカみたいな事故起こすんだよ」
このときの夏実の顔はもう、傑作だった。逆立ちした犬が雪道をフェラーリでドリフトしていても、こんな驚いた顔はしない。
「ばーか」
僕は何のためらいもなく言い放った。
「ばーかばーか」
「……グスッ」
夏実は鼻をすすり上げた。
「ああごめん。言い過ぎた」
「ちがうよ、もう……下手に慰められるより、ずっと……」
殴られる覚悟だったのに、夏実は今にも泣き出しそうなほど顔をくしゃくしゃにした。
「ごめ、ん……なさい」
とうとう彼女は顔を覆って泣き出した。それは僕に見せた、いや、他人に見せた初めての涙だった。
はじめは声を抑えていたけど、途中からあきらめて、これでもかと声を上げた。今の今までため込んだ泥を全て吐き出すように。人気のないロータリーにその泣き声が孤独に響き渡った。
ようやく彼女が本当の姿を見せてくれた。それは触れたら壊れそうなほど脆く、小さかった。
どこにも行ってしまわないように、僕は強く彼女を抱きしめた。夏実は僕の胸に顔を押し当てて、さらに泣いた。
永遠に思えるほど時間が経って、夏実はのっそりと体を起こした。
「今の、やっぱりなかったことに、できない?」
目もとは真っ赤に腫れていて、声もかすかに震えている。どこか照れくさそうだ。
「ダメ」
僕はキッパリと言った。
「ここまでしておいて、今さら忘れろなんて、卑怯だと思わない?」
「……卑怯じゃないもん」
まるで小さな子供みたいな意地の張り方だった。
「でも、事故は事故じゃん」
「もう、いいでしょ。私が悪かったです。もっと安全運転します」
「そうしてくれると助かる。これ以上心配しなくて済むから」
夏実はサッと目を逸らした。
「そ、そもそも、間庭君が呼び出さなければ事故らずに済んだのよ」
痛いところを突かれた。
「で、大事な話って何だったの? そのために呼んだんでしょ?」
一転、夏実が攻勢に出る。でも、僕は退かなかった。
「ハッキリさせたかったんだよ。僕と、夏実とのこと」
夏実の口が引き締まった。
「ちゃんと蓮花には言ったから。つき合えないって」
「……それが、私に何の関係があるの」
「あるって。大ありだって」
「どこがよ」
僕を見る彼女の目は氷のように鋭く、僕の心を突き刺した。
「それは……」
「そんなんだから!」
言葉が途切れたところを、すかさず夏実が拾った。
「間庭君はね、いちいち回りくどいの。言いたいことがあるなら直接言ってよ」
再び彼女の目尻に雫がたまる。目は、口ほどに物を言う。
「そ……」
僕も負けじと反撃する。
「そっちこそ、毎回毎回ストレートに言い過ぎなんだよ」
「昔からそうなの。二十年生きてきて今さら直せって方が無理な話」
ああ。もっといい雰囲気にしたかったのに、なぜか言い争いに発展してしまう。ロマンの欠片もない。
けどきっと、それが僕たちなんだろう。なんだかんだ、こうやって軽口言い合っている時間が、一番心地いい。
でも、このまま平行線をたどるのはもうたくさんだった。もう一歩踏み込まない限りには、これ以上の進展はない。
すでに僕は気づいていた。夏実が本当に求めているもの、それは自分に立ち向かってくることだ。彼女の攻撃を一方的に受け入れるだけでなく、同じように攻撃し返す。そうやって彼女の固い殻を破って、深く心を通じ合わせる。これが必要なことだった。
だから、僕が本気で彼女を求めているなら、腹をくくって攻めるしかないんだ。
「いつも思うけど夏実はさ、ちょっとしゃべりすぎだよ」
「だから?」
「少し黙った方がいい」
「じゃあ黙らせてよ」
夏実はジッと僕を見据えた。その目は覚悟を持って開かれている。
もう今しかない。
「そうか……だったら」
さっきよりも強い力で夏実の体を抱き寄せる。鼻先がぶつかる距離で、音がするくらい視線がぶつかり合う。僕はそっと唇を重ねた。一気に腹の底から熱いものがこみ上がってきた。一度離してから、もう一度口づけをする。今度はもっと強く、激しく。夏実もそれに応えるように、僕に絡めた腕に力が入った。
僕らは息をするのも忘れるほど一心にキスをした。
やがて名残惜しく唇を離し、僕はささやいた。
「続きは、怪我を治してから。いい?」
「…………」
夏実は夢を見ているかのように頷いた。
辺りは時間が止まったかのように静かだった。それでも時計の針は一時になろうと動いていた。
「やるときは、やるんだね」
「僕も男だよ」
「そういうの、時代遅れ」
「それ、お前が言う?」
「うるさい」
照れ隠しなのはバレバレだった。
「帰ろう。立てる?」
「一人で立てるから」
この期に及んで夏実は強がった。なんて素直じゃない。
「無理しないで。ほら」
僕は先に立ち上がって、夏実の手を取った。彼女はしぶしぶ立ち上がる。
「……じゃあ、夏実が運転する?」
「……バカ」
そうつぶやいた彼女に肩を貸してやった。ゆっくりと、二人で歩く。
怖いくらいだ。本当に夏実と、ここまで近づけるなんて。実はこれは全て夢で、現実の僕はサー棟の駐車場で凍え死んでいるかもしれない。
車に乗り込んでエンジンの鼓動を聞いたときにようやく、僕は生きていて、今が現実であると実感できた。おかげで隣に乗っている人のことを意識させられて、胸がいっぱいで思わず叫んでしまいそうだった。
この先、僕らがどこまで行けるかはわからない。雪のようにすぐ消えてしまうかもしれないし、この車が走り続ける限りかもしれない。
不安はあったけど、同じくらい希望もあった。
夏実を選んだことは、絶対に間違いじゃない。これだけは自信を持って言える。だから、きっと大丈夫だ。
車を走らせると、薄く積もった雪に轍が残った。
これがどこまでも続くことを願って、僕はアクセルを踏み込んだ。
「これでめでたしめでたしってことだね」
「まだですよお。むしろ、今夜こそ一番の勝負なんですから」
年が明けてから久しいある晴れの日、僕は真田さんの店を訪ねていた。相変わらずほとんど車は来ない。真田さんが洗っている一台だけだ。
今夜、夏実の回復祝いとBMWの退院記念にデートをすることになっていた。そのことで、僕は真田さんに相談しに来ていた。
朝から緊張しすぎて、僕は車で走り回っていた。何しろその辺の経験に疎いもので、振る舞い方がまるでわからない。蓮花とも一度やらかしたし。
その蓮花とは今も変わらず研究室で会っている。色々吹っ切れたのか、今では気兼ねなく話ができている。
バイトも続けていて、店長にしごかれながらせっせと働いている。あの人も、よくつき合ってみるといい人だ。映画に詳しいのには驚いた。
そんなわけで、色々あったけど僕は上手く日々を過ごしている。
真田さんは手を止めた。
「大丈夫だって。あの夏実ちゃんを落としたんだから、自信もっていけばいい」
真田さんはあっけらかんと笑ってみせた。
「ほら、あれ言ってごらん。覚えてるでしょ?」
「直感、ですか」
真田さんはにっこりと頷いた。
直感。忘れるはずない。僕はその言葉に救われた。おかげで、夏実とここまで近づくことができた。
しかし、これで終わりじゃない。この先も僕はいくつもの選択をすることになる。人生を左右するものだってある。でももう怖くない。そこで悩んだら、最後は自分が信じる方を選べばいい。
もし、そのときに一緒にいてくれる人がいたら。それがもし夏実であってくれたら。もう無敵だ。
「実はさっきまで、夏実ちゃんが来てたんだよね」
「え、マジっすか」
考えることは同じか。
「うん。あんまり上手じゃなかったって」
「は?」
真田さんは大口開けて笑った。
あの夜、あんまり夢中になりすぎたせいで怪我の回復が遅れたことで、僕は夏実にこっぴどく怒られていた。
「でも、すごく喜んでたよ、あの子」
「はあ」
そういうことは直接言ってくれないんだから。やっぱりあいつは素直じゃない。
真田さんは洗車機のホースで車の泡を一通り落とした。見事につやつやのボディが現れる。
「ちょっと手伝ってくれる?」
不意にタオルが投げつけられた。
「え、なんでですか」
「拭き上げ手伝ってくれたら、必殺技を教えるよ」
「必殺技?」
真田さんは不敵な笑みを浮かべた。
「そう。どんな女の子も一発で物にできるとっておき。昔、これで嫁をゲットしたこともある」
「え、聞きたい!」
僕は一心不乱に車を拭いた。それはもう隅々まで、一滴も残さないように。心なしか、停めてある僕の車が恨めし気にこっちを見ているような気もするが、多分気のせいだろう。
洗車が終わり、お客さんも出ていったところで、僕は待ちきれずに聞いた。
「で、必殺技って?」
「え? ああ、それね」
真田さんはとぼける。
「そんなものはない」
「え」
膝から崩れ落ちた。タダ働きかよ。
うなだれる僕の背中を、真田さんはバンと強く叩いた。
「しっかりしな。そんなお手軽な技に頼ろうとしているうちはまだまだってことだよ」
それもそうだ。僕は観念して立ち上がった。
「男だったら、車も女の子も乗りこなしてなんぼさ」
頼れる男の言葉は重かった。
「流石です」
具体的なアドバイスじゃなかったけど、僕は心強かった。いつだって真田さんは、前に進むための力をくれる。それを活かすか殺すかは僕次第だ。ガソリンスタンドの店員らしいというのは、少しこじつけが過ぎるか。
給油を終えて、僕は車に乗り込んだ。ちゃっかり安くしてもらってちょっとラッキー。
「ありがとうございます。頑張ります」
「おー。頑張れよ」
ギアを一速に入れ、サイドブレーキを下ろそうとしたとき、僕は思いとどまって、真田さんの方に向き直った。
「真田さんは、車と奥さん、どっちが大事なんですか?」
これには真田さんも目をぱちくりさせた。ぺチンと額を叩き、天を仰いで笑った。
「そりゃ、選べないわ!」
最後までお付き合いいただきありがとうございました。

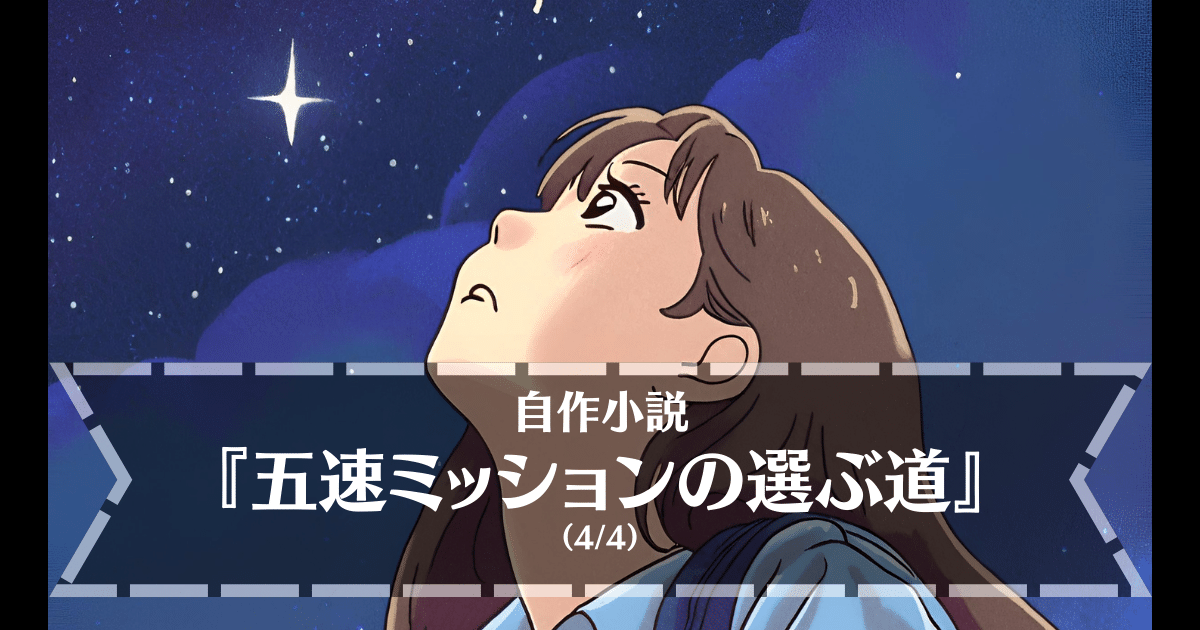






コメント