公開中の作品から数えるとほぼ1年振りの新作です
いつも通りカクヨムにも投稿しています
お楽しみください
生きていると一日に百回くらいは、選択肢にぶち当たる。
何を着るかとか、何を食べるかとか、もしかしたら玄関を出て最初にどっちの足を出すかだって、無意識に選んでいる。
一日のほとんどは些細な選択の連続だけど、一生という長い目で見たら、何度か重大な選択をする場面が出てくる。就職とか、家を買うとか、結婚とか。
思い返せば、大学三年生になる僕はこれまでの短い人生で一度も、大きな選択をしたことがなかった。直近で最も大きな選択の機会は大学進学だ。しかし今通っている大学も、自分の学力で行けるところがそこしかなかった、という消極的な理由で選んだ。私立でなく国公立にしたのは、そっちのが就職に有利だから、という周りの声があってのことだ。
それどころか、小さな選択すらしてこなかった。
幼少期から僕は甘やかされて育った。兄が一人いるけど、年は十個も離れていたからえらく可愛がられた。過保護ぎみの両親からも溺愛されて、欲しいものは何でも与えてもらえた。自分で選ばなくても、誰かが代わりに選んでくれたし、選ばなくても困ることもなかった。
そんな風に育ったためか、いつしか僕は、自分で選び取ることをしなくなった。
生活には何一つ不自由していない。ただ少しだけ、人より長い時間考えてしまうというだけだ。あるいは、逃げているのかもしれない。飲み会では隣の人と同じ飲み物を頼むし、サブスクでみる映画もおすすめに出てきたものか、人におすすめしてもらったものだ。
こんなこと、気にする人なんてまずいない。おそらく多くの人は、自分が日常的に選択肢に向きあっていることすら意識していない。意識しなくても大丈夫なくらいに、器用に生きているからだ。
でも、あいつと出会ってから全てが変わった。
常に自分の力で道を進むあの強さに魅せられた。少しでも近づきたいと思った。そのために何度も傷ついたし、他人を傷つけたりもした。
でも一方で、学んだこともある。僕がどれだけ自分で選んでこなかったかを。そして、自分で選び取ることの大切さも。
そして時々考えることがある。
僕が選び取った道は、果たして正しかったのだろうか、と。
三年生になってからアルバイトを始めた。
金に困ることはなかったけど、免許を取ったことがきっかけで車の購入が視野にあった。
アパートから徒歩三分の場所にある、古ぼけたガソリンスタンド。友人の紹介だったけど、どことなくゆるい雰囲気が気に入って申し込んだ。
通りの多い交差点の角にあって微妙に入りにくい。来店するお客さんといったら常連の老人か、旅行者くらい。立っているだけの時間が多く、暇疲れになりそうな店だった。仕事が少ないからありがたいけれど。
「真田さん、おはようございます」
「おー、おはようさん」
窓ふきの手を動かしながら真田さんがこちらを向いた。この店の店長だ。この人の顔を見るだけで、安心して仕事ができるような気がした。
四十代半ばとは思えない若々しい風貌の真田さんは、まさにこの店の大黒柱だ。仕事が早く、面倒見もいい。お客さんの対応は丁寧なだけでなく、それぞれの車の状態やお客さん自身の性格まで考えている。その人当たりのよさは僕らにとってもありがたく、急用が入ってシフトに出られなくても、真田さんには気楽に相談できた。こんなオンボロのスタンドにはもったいない人だ。
「知久、名札付け忘れてるよ」
「ああ、すみません」
うっかりしていた。一度控室に戻り、ロッカーから名札を見つける。
「間庭知久」という名前を左胸に掲げ、店頭に出た。
僕がいないわずかな間に新しく客が入っていた。やけに古い車だった。一発で外車だとわかる。真田さんがそのお客さんと話をしていた。相手は若い女の人のようだった。二人とも楽しそうに、ショックがどうとか、クラッチがどうとか、車の話をしていた。真田さんはいつも以上に親し気な顔をしていた。
「じゃあまた来ますね」
「はーい、また来てね」
女の人が乗った白い小型車は、滑るように走り出して交差点の中心へ進入し、軽快に走り去った。初めて見る車の動きだった。まるで生き物のようだ。
「真田さん、今の人は?」
「よく入れに来る子だよ。知久と同じ大学」
車が去った先を見据えながら真田さんは言った。
「え、大学生なんですか。学部は?」
「文学部だよ。もしかして顔見たことあるんじゃない? 御沢夏実って子だけど」
御沢夏実。
その名前の響きは覚えがある。
「え、その人と僕、同じ授業取ってるんですよ」
「あ、そーなの?」
「はい。まあ、喋ったことはないんですけど」
そうだ。英文学の授業で顔を見たことがある。
「なんか、珍しい車乗ってますね。なんてメーカーですか、あれ」
「プジョーって分かる? あのライオンのマークの」
似たようなマークが三つくらい頭に浮かんだ。よくわからないけど、動物のマークってことはお高いのだろう。
「あーなんとなく、なんとなくですけどわかりますよ」
「あれのふっるーい車だよ。もう二十年前の車になっちゃうのかな」
「すげえ。ほぼ同い年じゃないですか」
「いい趣味してるよ。若いのに」
表情からは嬉しさがにじみ出ている。真田さん自身も根っからの車好きで、何台も外車を乗り継いでいるから、通ずるものがあるのだろう。ちなみに真田さんが今乗っているのはかっちょいいBMWだ。
「高いんですか?」
「そうだねえ。安くはないし、あとあの手の車は変なところが壊れるからね。修理費だけでもう一台買えるよ」
「ひえー」
どんなお嬢様なんだろうか。そうでなくても相当に変わった人だ。
「そうか顔見知りかあ。今度乗せてもらったら?」
「いやいいですって――あ、らっしゃいませー!」
そこへふらっとお客さんが入ってきた。僕が向かう。
「いらっしゃいませ」
「満タンと、あとオイル交換してくれる?」
「はい、オイル交換ですね。かしこまりました」
僕は声を張り上げた。
「店長オイル交換ー」
「はいよー」
作業が入ったから、雑談は一旦終わりだ。
研究室に入ると、見慣れた顔があった。僕に気づくと、その短いくせっ毛のボブが揺れた。
「おつかれ」
「あ、おつかれー」
三原蓮花。文学部文学科英文学コースで二人しかいない三年生のうちの一人。もう一人は僕だ。
英文の研究室、といっても理系と違ってただの自習部屋だ。部屋の壁に沿って本棚が置かれ、文学作品や参考書が並べられている。長机が四つ合体した大きい机が二つあって、その上にはこれでもかと物が散乱している。本はともかく、割りばし、ティーバッグ、ホチキス、チョコレートの箱と、やりたい放題。そのほとんどは蓮花の仕業だ。
そもそも人が少ない英文学コースで、さらに研究室に来てまで勉強するような真面目な人となると、蓮花か僕くらいしかいない。ここは実質二人の共同の部屋みたいになっていた。
僕は入り口に一番近い場所に座った。蓮花はその対角線上、入り口から一番遠い場所に座っている。これが二人のいつものポジションだった。
彼女は机にプリントを広げていた。
「予習?」
「うん、まあね」
木曜二限の英文学の授業で使う資料だった。この授業では事前に決められた作品の一部分を読んで、自分の考えを用意してくる。分量こそ多くはないけど解釈が難しく、負担が大きい。それに、授業では三、四人のグループを作ってディスカッションをするため、サボることもできない。
「僕もまだ読んでないな。難しい?」
「結構難しいかも。まあでも、誰だっけ、一人めっちゃ喋ってくれる人いるでしょ?」
「御沢さん?」
そうそれ。と蓮花は指を差した。
「あの人すごいよねー」
偶然だろうか。このところ御沢夏実という名前をよく聞く。彼女は同じ文学部でも言語学科に所属しているが、いくつか文学の授業も取っているらしい。その一つが僕と被っている。
「一緒の班になるのをお祈りするかなあ。はあめんどくさ」
蓮花はだるそうに机に突っ伏した。
「やるしかないんだから」
「代わりに読んでよー」
「なんで」
あしらいつつ、僕は僕でパソコンを立ち上げて自分の課題に取りかかる。
次第に会話も減って、キーボードを打つ音と、ときどき紙をめくり、何かを書き込む音だけが聞こえるようになった。
僕はなんとなく集中できず、窓の外を眺めた。遠くに山が見える。手前にはサークル棟と、サッカーグラウンド。見慣れた景色をぼんやりと瞳に映しながら、僕は御沢夏実のことを考えていた。
なぜだろう。週に一度目にするだけの、顔見知りですらない学生が妙に心に引っかかる。変わった車に乗っているからだろうか。どんな人で、どんなことを考えて生きているのか、ぜひとも知りたかった。
「グレートギャツビーの話の構成ってノルウェイの森と似てますよね。あ逆か、ノルウェイの森がギャツビーと似ているのか」
ディスカッションが始まると、夏実は僕を含めたグループ四人の中で最初に話し始めた。文体から話の展開、キャラクターの背景を引き合いに出してグレートギャツビーとノルウェイの森の関連性をひたすら説明している。彼女の迫真の語り口は、他の学生に一言も喋らせない。
今週の木曜二限で、僕は初めて夏実と同じグループになった。
改めて正面から見ると、夏実はかなり美人だった。おでこを大胆に出した茶髪のロングヘアーは肩の辺りでゆるくウェーブしている。顔の輪郭は縦長気味の卵形で、キリっとした目元は、日本人の割には彫りが深い。質のいいパーツがあるべき場所に配置されていて、その奇跡的なバランスが「美人」というオーラを常に発し続けていた。
しかし彼女は想像を二段階くらい超えたおしゃべり人間だった。そのよく回る口のせいで美貌が損をしている。もったいない、と赤の他人ながら思った。
「……と、いうことなんですけど、他に意見あります?」
「……」
グループにしばし沈黙がおりる。脱力感さえあった。
「……じゃあ」
「これは関係ないんですけど、グレートギャツビーって映画化もされていて、それも二本あるんですよ」
僕が口を開きかけても、夏実はそれを食ってまた喋り出す。
「昔の方は知らなくても、新しい方は観たことある人いるんじゃないですか?」
「あ、観たことある。ディカプリオのやつでしょ?」
僕が食い気味で答えると、夏実は待っていましたとばかりに目を輝かせた。
「そうそう! で、ニックの役がトビーマグワイアなの。この二人が共演してるのがほんとに熱いの。この二人って実は親友同士で――」
突然話が脱線し、夏実は映画を語り始めた。止める人はいない。主導権を握っている夏実は話を広げに広げ、収集がつかなくなったグループはついに暴走特急と化した。
「トビーマグワイアってわかります? 一番面白いスパイダーマンやった人ですよ。ほら、ノーウェイホームにも出てきたじゃないですか」
「サムライミ版はリアリティがあっていいよね。スーパーヒーローと日常との姿のギャップに葛藤する姿とか」
映画なら得意分野だ。僕は負けじと食らいついた。
「そう! まさにそう! わかってくれる人がいた。あれは傑作だよね」
彼女の知識の広さ、深さには目を見張るものがある。こちらが何を聞いても答えてくれる守備範囲の広さもある。どんなボールを打っても返してきそうなディフェンス力は、ジョコビッチに匹敵するものがある。
他の二人を置き去りにしたまま、僕らは映画談議にふけった。初めて喋ったのに、初めてじゃないような感覚があった。相手もそう思っているのかは分からないけれど。
「三作目も面白い映画ってなかなか珍しいよね。例えば何かある?」
「んー、ミッションインポッシブルは2より3の方が面白いかもしれない」
「なるほど。スターウォーズのエピソード3は?」
「あれは公開順で言うと六作目でしょ?」
「そうだった」
「そうだよ」
一体何のディスカッションをしているのかわからなくなりそうだった。
結局、時間一杯まで映画の話が続き、作品自体の解釈は深まらずに終わった。
授業後、鞄を持って立ち上がったところの夏実を捕まえた。このチャンスを逃すつもりはない。
「うちのスタンドによく来てるよね?」
「そうだけど?」
大きく鋭い眼に見つめられ、グッと背中に緊張が走る。
「最近バイトするようになって。で、この前見かけたんだ」
「偶然ね。でも、よく覚えてたね」
「そりゃあんな車乗ってたら忘れないよ」
夏実の見えざる尻尾が振られた。
「そう? でもおんぼろだよ」
「かわいい車だよ。プジョーっていうんでしょ?」
「そう! よく知ってるじゃん。あの車はね、106って言って、数字の106って書いてイチマルロクって読むんだよね。それであれは2003年式のモデルでS16ってグレードなの。それで……」
夏実は待ってましたと言わんばかりに車の説明をおっぱじめた。
何を言っているか半分も理解できななかったけど、彼女は殊更に軽さを強調していた。1トンを切る重量でもって、1.6リッターのエンジンのパワーを余すことなく使い切るのが楽しいらしい。
夏実はそれから三十分近くもの間、自分の車について語った。よくそこまでしゃべれるなと感心してしまう。
一通りしゃべって満足したのか、夏実は話題を変えた。
「間庭君、よく映画みるの? 結構知ってそうだったけど」
「ぼちぼちかな」
自慢じゃないけど映画はそんじょそこらの人よりは数多くみている。でもきっと、彼女はその遥か上をいくのだろう。
「何か好きな作品ある?」
「うーん。どれかなあ」
「いくつかあるってこと?」
僕は返答に詰まった。選択肢が多いだけに、むしろセンスが問われる。変なタイトルを出したらイヤな顔をされるだろう。それが美人な女の子と来れば、傷はより深い。
ショーシャンクなんてありきたりすぎるし、変にカッコつけてセブンとかでも変だし。ここはひとつ……
「まあ、ありきたりだけど、テルマルイーズとか、かなあ」
夏実の瞳の中で星がきらめいた。それはもう、とびきりの一番星だった。
「すごい。いきなりそれが出てくる人とはじめて会った」
気分が高ぶって、そのうち踊りだすんじゃないだろうか。インド映画みたいに。
「はは、どうも」
「こんな面白い人が身近にいたなんて。もっと早く言ってくれたらよかったのに」
ここまで喜ばれるとかなり照れくさい。
「今日はこの後授業あるの?」
「四限があるよ」
「その後は帰る?」
夏実は期待に満ち満ちた目を向けてくる。
「まあ、帰るよ」
「じゃあ授業終わったらサー棟の駐車場に来て。私も今日は四限で終わりだから」
決まりね、と言い放ち、夏実は僕の返事を待たずに教室を出て行った。
サー棟とはサークル棟の略称で、各サークルの部室が一堂に集結している建物のことだ。キャンパスを一度出て道路を渡った先の丘の上にあり、周囲を木で囲まれているから、意識していないと存在にすら気づかない。そのサー棟前には二、三十台もの車が停められる駐車場もあり、いつも学生の車で埋まっている。
長い階段を上がり駐車場に出ると、夏実があの白いプジョーのボンネットに腰掛けていた。車のカタログからそのまま出てきたような美しい姿に、僕は息を呑んだ。
「来たね。無視して帰られたらどうしようって思ってた」
「律儀な男なんで」
言いながら僕はプジョーの全身をじっくりと見た。
曲線が少ないボディの割に、今まで見たどの車よりも個性的だった。軽自動車とさほど変わらないサイズだけど、ボンネットが長い。天井の切れ目からお尻にかけての斜めのラインには目を惹かれるものがあり、まるで動物の後ろ姿でも見ているような息づかいを感じる。シンプルかつ妥協のない均整のとれたデザインは、西洋美術が培った美的感覚でないとなしえないものだろう。
「乗って。家まで送るよ」
プジョーに体重を預けながら、親指で車内を差した。その仕草すら様になっている。
「いいの?」
「ダメならはじめっから言わない」
それもそうか、とつぶやいて僕は助手席のドアノブに手をかけた。
「あれ、運転するの?」
はじめ、僕は夏実が何を言っているのかわからなかった。窓から車内を覗くと、僕はすぐに納得した。
「そうだ、これ左ハンドルだった」
ハンドルが座席の左側についていた。実際に見てみると、異質だ。
「逆側だけど怖くないの?」
「別に。ほとんど変わらないから」
夏実は立ち上がって言った。
「ほら、そっち乗って」
僕は車の後ろを回って右側の助手席に乗り込んだ。ドアはバシッと気持ちよく閉まった。
車内も一風変わっていた。天井は拳一個がギリギリ入るくらいで、足元は右側の出っ張りがちょっと邪魔だけど足をのばすことはできる。決して広くはないけど、圧迫感はなかった。この辺の空間の使い方もどこか日本の車とは違う。内装は実にシンプルで、中央にエアコンやハザードランプ等のスイッチがコンパクトにまとまっている他にスイッチ類は見当たらず、ナビもついていない。右側に座っているのに、前に何もないのが面白おかしかった。
夏実が運転席に座り、シフトレバーを何度か動かしてからエンジンをかけた。手慣れた動作だった。後付けのカロッツェリアのオーディオからサラブライトマンの曲が流れ出した。センスがいい。
僕と夏実は結構ご近所さんだった。歩いて二分もかからない場所に住んでいるそうだ。二年も暮らしてて一度も気づかなかった。
「シートベルト締めた?」
「締めたよ」
「よし、行きます」
シフトを一速に入れ、サイドブレーキを下ろすとすぐにプジョーはゆっくりと歩み出した。
あっという間に僕はこの車の虜になった。
車というのは静かで揺れが少なければ乗り心地がいいものだと思っていた。このプジョーはロードノイズが大きく、段差を越えるときは段差の分だけ上下する。曲がれば曲がった分だけ車体が傾く。それなのに、乗り心地は最高だった。
地面との距離が近い。車内にいながら外を走っているように感じる。窓から手を出したら触れるんじゃないだろうか。
シートの座面からは道路の細かい凹凸さえも伝わってくる。カーブを走ると、タイヤが地面を掴んでいる感覚がよくわかった。
それに、とにかく動きが軽快だった。特に交差点では面白いように曲がった。
「どう? 念願の車に乗った感想は」
そう訊ねる夏実はどこか誇らしげだった。
「すごいよ。こんな楽しい車、初めて乗った」
「そりゃどうも」
そう言って彼女は三速へシフトチェンジした。ショックを出さずにギアを繋ぐと、思いきりよくアクセルを踏み込み加速、さらに四速へシフトアップして車をスピードに乗せた。
車の作りもさることながら、彼女のドライビングテクニックもまた極上だった。
ハンドル捌き、ペダルワーク、シフトレバーを握る手つき。そのどれも無駄がない。それだけでなく、全ての動作は丁寧で、車の姿勢を手に取るように制御している。彼女がハンドルを回すと、円を描くように重力が移動した。おかげで、スピードが出ていても僕はゆりかごに揺られているかのように安心できた。
こんなの反則だ。これだけ美人な子が、とびきりお洒落な車に乗っていて、しかもめちゃくちゃ運転がうまい。
大通りを外れ、住宅地へ向かう。橋を渡った先のわき道から小型車が一台飛び出してきた。明らかな割り込みだった。
「おい!」
と言ったのは僕ではなく夏実だった。喉のどこにしまっていたのか、普段のしゃべり方からは想像もつかないほどドスの利いた声だった。
「そのタイミングで出る普通? うわうわほら、全然加速しない。出るなら覚悟持って出なさいよ。そんでアクセルを地の底まで踏み抜けそうじゃないならそんなカスみたいなタイミングで出んなよ!」
夏実は車の鼻先を相手のギリギリまで近づけた。少しでもブレーキを踏まれたらぶつかる距離だ。それからクラッチを切り、エンジンをレッドゾーンまでふかした。
僕は唖然として夏実を見た。彼女は牙をむいて前の車を威嚇していた。
都合よく先の信号が赤になった。反動のないブレーキで車を止めると、夏実は僕を見て、気まずそうに目線をまた前に戻した。
「ごめんなさい。私つい」
怒りはもう収まっていた。それどころか額をハンドルにこすりつけてまでして反省している。
「運転するときはいつもこうなの。ヘンな動きをする車を見ると無性に腹が立って……」
なるほど。こんな彼女にも欠点はあった。ハンドルを握ると性格が変わることだ。それも、重度の。
信号が青に変わると、夏実は充分以上に車間距離をとって走った。
「いつもビックリされるでしょ。隣に乗せた人に」
「いや、間庭君がはじめて」
「じゃあいつもはそんな怒らないんだ」
「そうじゃなくて横に乗せたのが、間庭くんが初めて」
「え、そうなんだ」
僕はおずおずと頭を下げた。
「それは恐縮です」
意外だった。大学生で車を持っているやつは、友達にいいようにタクシーにされるのが当たり前だ。こんなに運転が上手ければ、なおさらそうだと思えるが。
そこまで考えて、悲しいことに気づいてしまった。もしかして御沢夏実は、友達が――
僕は頭を振った。きっとたまたまだ。それか、自分の車を大事にしているのだろう。
アパートに着いた後、夏実は車を降りようとする僕を引き留めた。
「次さ、授業終わったあとに昼ごはん行こうよ」
「喜んで」
思わぬ誘いだった。そこまで僕は夏実に気に入られたのか。
「間庭君のおごりだよ?」
「マジ?」
顔をしかめると、彼女は口を大きく開けて笑った。
「冗談だよ。また来週ね」
なんだよ。思ったよりおちゃめなやつだ。
「じゃあまた。ありがとう、乗せてくれて」
ドアを閉めると車はすぐに走り出し、あっという間に見えなくなった。その後もしばらく、僕は車が去った影を眺めていた。
キャンパスに点在する食堂の中でも、一番マシな食事を出すのがこの中央食堂だ。文系と理系のキャンパスを結ぶ二本の橋の中継点にあり、昼時は文理両方の学生で賑わっている。中央と名乗っている割に、二番目に大きい食堂というのが謎なところだ。
僕と夏実は六人掛けのテーブルを挟んで向かい合っていた。僕はカレーで、彼女はラーメンだ。券売機の前で悩んでいたら勝手に押された。
髪を結んだ夏実は、恥じらいもなく豪快に麺をすすっていた。咀嚼しながら何度か頷いている。いちいち仕草が食通みたいだ。
「今さらだけど、間庭君って免許持ってるの?」
飲み込んでから夏実が訊ねた。
「持ってるよ」
「オートマ限定?」
祈るような視線を僕に向けている。
「いや、マニュアルの方」
僕が応えると、夏実は安心したように水を一気に飲み干した。
「それは偉い。偉いよ」
「そんなかなあ」
「だって、身の周りの人なんてみんな限定でしょ? 男の子だって限定だし」
彼女の言う通り、今やほとんどの人が運転免許をオートマ限定で取っている。僕も父親に半ば強制されてしぶしぶマニュアルで取っただけで、何も言われなければ限定だっただろう。なんせ、今の時代は必要がないからだ。
「まあ、別にマニュアルの車なんてほとんどないから」
多くの大学生が口にするこの文句はしかし、
「それは甘え」
彼女にバッサリと切り捨てられた。
「オートマ限定なんて、補助輪つけて自転車に乗るようなものだよ。それにさ、必要ないからって取らないのも理解できない。マニュアルに乗れないとオートマで安全に運転できるわけないのに」
急に毒舌を発揮した夏実に僕は気圧された。
僕が黙ってしまったことに気づくと、彼女は申し訳なさそうに目を伏せてスープをひと口飲んだ。
「ごめんなさい。また暴言を」
授業のときや運転してるときもそうだけど、夏実は口に戸が立たないタイプだ。一度思ってしまったら、口に出さないと気が済まない。
「でも、ちょっとわかるかも。車校でマニュアル運転してからオートマ運転すると勝手に車が進んでく感じがして怖かったから」
「そう。そうでしょ?」
彼女が同意してくれて、僕は胸をなでおろした。汗ばんでいるのは、単にカレーが辛いだけではない。
もうひと口麺をすすってから、夏実は言った。
「車はまだ買わないの?」
「まあ。安いのがあったら」
「安いのって例えば? 208のモデルチェンジ前とかねらい目だよ」
ニーマルハチという響きで、同じプジョーの車だとわかった。そんな車を大学生に勧めてもらっても困る。
「外車はやめとくよ。別に普通の車で」
「普通の車って例えば?」
彼女の質問はどこか、鋭利な響きがある。面接でも受けているようだ。
「いや、軽とか」
「間庭君、それは一番やめた方がいい」
僕を見つめる夏実は、助言をすると同時に懇願しているようにも見えた。
「どうして? みんな軽に乗ってるけど」
「軽自動車なんてカス。あんなのは車輪がついただけの箱よ」
隣のテーブルで談笑していた男子の一人がギョッとした顔でこっちを見た。
「でも、燃費もいいし、小さいから運転しやすいんじゃないの?」
「いいわけないじゃない。あれに毎日乗るって考えたら、椅子に縛りつけられて瞬きもできない状態で暴力的な映画をひたすらみせられる方がまだマシよ」
「それ時計じかけのオレンジ?」
「よくわかったね」
ネタが伝わって上機嫌になったのか、夏実は矛を収めた。
とんでもない暴言だったけど、全く間違っているとも思えなかった。彼女の言うことには不思議な説得力がある。
「でもごめんなさい。言い過ぎたかも」
「まさか。むしろそれくらい言ってくれた方がいいよ」
「ほんと?」
「うん。ここまでズバッと言えるのは長所だよ」
一瞬、夏実は戸惑いを見せた。
「そんなの、言われたことなかった」
「わからないのがおかしいんだよ」
「ふふ、そうかも」
それから満足げに微笑んだ。その美しさは彼女の持つ毒を知った今、より際立って見えた。
「今日も四限終わったら帰るの?」
昼飯もすっかり食べ終わり、食器を片づけながら夏実が訊ねる。
「帰るけど、また送ってくれるの?」
次に何が来るのはわかっていた。
「送ってくよ。でも」
夏実は車の鍵を出して、トリコロール柄のキーホルダーに指をかけてくるくる回した。
「今日は、運転してみる?」
「え、いいの?」
「実際に運転してみないとわからないでしょ?」
「そうだけど、左ハンドルなんて」
「同じよどっちも同じよ」
微妙に伝わらない小ネタを出すな。
「でも、ぶつけたら悪いし」
「それなら平気」
夏実は妙に自信ありげに言った。
「平気って? なんで?」
「私の車、もともと母親が乗ってたの。私が免許取った辺りで乗り換えることになって、譲ってもらったんだけど――」
ゆっくりと夏実は語る。
「うちの母親は昔っから運転が下手くそで、今まで乗った車は必ずどこかしらに傷をつけたりへこませたりしてたの。廃車にしたこともあったかしら。でもね、この車だけはどこにも傷が入ってないの。不思議でしょ? まるで意志があるみたいに、危険を避けてくの」
冗談みたいな話だ。どうせ偶然なんだろうけど、夏実が言うとリアリティがある。
「だからきっと、間庭君が乗っても大丈夫」
「ハービーみたい」
「それなら私の車はラブ・キャットね」
「ライオンじゃなくて?」
「猫足だから」
「なるほど」
この辺のネタが伝わるのが、夏実の変態なところだ。もちろん、いい意味で。
「そういや、夏実はぶつけたことはないの?」
「私?」
夏実は大げさに笑ってみせた。
「ぶつけるわけないじゃん」
「他の車に乗っても?」
「もちろん。絶対ぶつけたりしないよ」
「そんなこと言って、もしぶつけたらどうすんの?」
夏実は口もとに人差し指を当てて考えた。
「もし、なんてものはないけど、もしぶつけたら――」
「桜の木の下に埋めてもらっても?」
「んふふっ。いや、死ぬほどバカにしてもいいよ」
大した自信だった。それも高い技術に裏打ちされているから言えることだ。
「言ったね?」
「もちろん」
自然と僕らは握手していた。
「じゃあ、また授業が終わったら駐車場来て」
夏実は鍵を僕に渡した。盗まれるという心配はどこにもないようだった。
その後の授業で、僕は鍵を机の上に出したままにしていた。ずっと視界にないとどこかへ失くしてしまいそうだったし、何より、あの車を運転できると思うとわくわくしてたまらなかったからだ。
「……」
「どうでしょう?」
練習のため大学構内を一回りしてきて、何とか駐車スペースに車を収めた。助手席に座る夏実はその間一度も口を開かなかった。
そもそも免許を取ってから丸一年まともに運転してなかったのもあった。その上、右手でシフトレバーを動かすとなると、もうわけがわからない。ハンドルは重くて上手く回せなかったし、ペダルが右に寄っていたせいでアクセルと間違えてブレーキを踏んでしまったことも何度かあった。こんな車を手足のように操っていたと思うと、夏実の技術の高さが改めてわかる。
夏実はでっかいため息をついてから言った。
「下手くそ」
やっぱり。
「左ハンドルはじめてだからシフトがぎこちないのは百歩譲って許す。でも何? アクセルもブレーキも、何もかも雑。しかも間庭君、周りを全然見てないでしょ? 危なくて仕方ないよ。一体教習所で何を教わってきたのか不思議」
「……ごめん」
言い方はキツいけど、中身はもっともだ。ぐうの音も出ない。
「いやいいの。少しずつ慣れてけばいいから」
彼女は無理にフォローしているようで、僕はかえってダメージを負った。
「それに、ぶつけなかったでしょ?」
「まあ、そうだけど」
確かに、あれだけグダグダな運転をしても、車には傷一つついていない。
「時間の問題だと思うけど」
でも、あの話はやっぱり信じられなかった。
「それはそれとして、車はどうだった?」
夏実が興味津々に訊ねる。
「たしかに全然違う。なんだろう。自分で動かしてる感じがする」
今まで乗ったどんな車とも違った感覚だった。夏実の横に乗っているときからそれは感じていたけど、実際にハンドルを握るとそれはもう劇的だった。楽しさが全身から湧き上がり、一気に弾ける。こんな車に乗っていたと思うと、羨ましくて仕方がない。
「間庭君がまともな感性を持った人で助かる」
まともじゃない感性のことをぜひ聞きたかったけど、聞いたらまたすごい暴言が出そうだったからやめた。
「でも、このままだとダメね。まるでダメ」
夏実は腕を組んで頭を振った。
「せっかく普通免許を持っているのに、こんな運転じゃ見てられない。それに、こんな身近に下手なやつがいるってのが許せない」
「悪かったって」
「違うよ。だからね」
夏実はその細く白い手を僕に差し出した。思えば、これが全ての始まりだった。
「私が鍛えてあげる。間庭君がまともに運転できるようになるまで」
こっちに選択権はなかった。
次回はこちら。



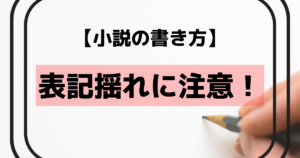





コメント